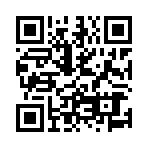2010年05月23日
【「確認」のムダ】
工場で機械のスイッチを入れるときに、誰かが機械の下で作業をしていないかを確認する。
この場合の「安全確認」は「ムダ」ではありません。
本当は、安全確認すら、不要にすればいいのですが、「安全第一」。
ムダと分かっていても、やるべき仕事になります。
部品を連続加工している時に、次工程の遅れ進みを確認して生産調整する。
この場合の「確認」は、間違いなく「ムダ」に入る作業です。
逆に後工程が、前工程の仕上がり具合を確認しながら、次の製造予定を立てる。
これも「ムダ」な作業です。
指示書どおりに作業すれば、決められた仕事ができる。
このような状態にもって行かないと、ムダが増えるばかりです。
そうはいっても、機械が故障することもあるし、ボルトが外れないために段取替えに手間取ることもある。
そのためのクッションとしての仕掛品は、どうしても必要です。
イレギュラーの事態に備えて、仕掛品は持っていなければならない。
そうでないと、作業者が手待ちになってしまうことがあります。
しかし、仕掛品の保有量は標準化しておかないと、仕掛品は際限なく増えることは間違いありません。
管理は、標準を決めて、標準を守らせること。
そんなに精度の高い標準でなくてもいいから、「時間当たり出来高(標準サイクルタイム)」「仕掛品の数量と置き場」は、最低限度数値化しておいて欲しいものです。
2010年05月22日
【「工程図」は使える】
仕掛品の悪さを認識してもらうために、あの手この手を試みています。
昨日行った指導先で、「工程図(製品工程図)」を書いてもらいました。
○ ⇒ ▽ ◇ の記号で、材料が加工され、移動され、一時滞留され、検査を経て製品に仕上がるプロセスを書き表すものです。
「一つの製品を作るのに、こんなに複雑な流れになっていたのか」
「仮置きがあるために、置き場まで運ぶ、置き場へ取りに行く、など、余分な作業が発生していることがよく分かった」
受講者の皆さんには、予定通りの感想を持っていただきました。
工場で価値を付加する作業は、○(加工)だけ。
そのほかは、◇(検査)も含めて、すべては「ムダ」なのです。
「工程図」は実にオーソドックスな手法ですが、労働の価値を認識してもらうためにも、大きな効果があるようです。
昨日行った指導先で、「工程図(製品工程図)」を書いてもらいました。
○ ⇒ ▽ ◇ の記号で、材料が加工され、移動され、一時滞留され、検査を経て製品に仕上がるプロセスを書き表すものです。
「一つの製品を作るのに、こんなに複雑な流れになっていたのか」
「仮置きがあるために、置き場まで運ぶ、置き場へ取りに行く、など、余分な作業が発生していることがよく分かった」
受講者の皆さんには、予定通りの感想を持っていただきました。
工場で価値を付加する作業は、○(加工)だけ。
そのほかは、◇(検査)も含めて、すべては「ムダ」なのです。
「工程図」は実にオーソドックスな手法ですが、労働の価値を認識してもらうためにも、大きな効果があるようです。
2010年05月20日
【まぐまぐでメルマガを始めました】
「生産管理ソフトに何百万円も投資したのに、うまく使いこなせない」
と泣きを見ている工場経営者があとを絶ちません。
コンピュータを導入するより前にやることがあるのに、それを忘れて、「コンピュータを使ったら合理化できる」と勘違いしておられる。
機械別の生産能力(時間当たり何個)をきちんとつかんでおられますか?
一人当たり出来高を把握しておられますか?
それらはきちんと標準化されていますか?
こういった基本的なデータをきちんと揃えないと、合理化も何もあったものではありません。
「そうはいっても、何百という品番があるし、品番ごとに同じ機械でも製造量が違うし・・・」
手計算でできないことをコンピュータでしようとするのは無理な話です。
「まずは数字をつかむ」ことです。
メルマガのテーマは、まずは諸悪の根源である、「工程内仕掛品半減」からスタートします。
スタートしたばかりで、読者数もまだ一桁です。
ライバルの先を行くためにも、ぜひ早めにご購読ください。勿論無料です。
『プロセス・マネジメント』を使えば90日で工場がよみがえる
と泣きを見ている工場経営者があとを絶ちません。
コンピュータを導入するより前にやることがあるのに、それを忘れて、「コンピュータを使ったら合理化できる」と勘違いしておられる。
機械別の生産能力(時間当たり何個)をきちんとつかんでおられますか?
一人当たり出来高を把握しておられますか?
それらはきちんと標準化されていますか?
こういった基本的なデータをきちんと揃えないと、合理化も何もあったものではありません。
「そうはいっても、何百という品番があるし、品番ごとに同じ機械でも製造量が違うし・・・」
手計算でできないことをコンピュータでしようとするのは無理な話です。
「まずは数字をつかむ」ことです。
メルマガのテーマは、まずは諸悪の根源である、「工程内仕掛品半減」からスタートします。
スタートしたばかりで、読者数もまだ一桁です。
ライバルの先を行くためにも、ぜひ早めにご購読ください。勿論無料です。
『プロセス・マネジメント』を使えば90日で工場がよみがえる
2010年05月19日
【ISO9001・14001ドッキング】
ISO9001と14001を別々に運用している会社が、一本化したいという問合せをよく受けます。
普通は別々に取得する場合が多いので、管理責任者もそれぞれ別の担当者が当たることも多い。
一本化して、定期審査も同時に受診するようにすれば経費削減のメリットもありますが、それよりも管理上のメリットの方が大きい。
「品質マニュアル」と「環境マニュアル」を一体化して、「マネジメントマニュアル」を作り、管理責任者も事務局も一本化すれば、非常にスッキリしたマネジメント体系が出来上がります。
9001を取得していて、新たに14001にチャレンジする場合も(逆でも同じです)、新たに「環境マニュアル」を作るのでなく、「マネジメントマニュアル」として、品質・環境を一体化したマニュアルを作ればいいのです。
その時は、ただひとつにまとめるというのでなく、これまで何年か運用してきて、使い勝手の悪い点も見えてきているでしょうから、当然改善する必要があります。
ただ、ドッキングの際に注意する点がいくつかありますが、それはおいおいご紹介していくことにしましょう。
☆お知らせ☆
まぐまぐから
メルマガを発行しています。
『プロセスマネジメント』で生産性を上げるノウハウを、実例を交えて順次ご紹介していきます。
ぜひご購読ください。
購読申込みはこちらから
普通は別々に取得する場合が多いので、管理責任者もそれぞれ別の担当者が当たることも多い。
一本化して、定期審査も同時に受診するようにすれば経費削減のメリットもありますが、それよりも管理上のメリットの方が大きい。
「品質マニュアル」と「環境マニュアル」を一体化して、「マネジメントマニュアル」を作り、管理責任者も事務局も一本化すれば、非常にスッキリしたマネジメント体系が出来上がります。
9001を取得していて、新たに14001にチャレンジする場合も(逆でも同じです)、新たに「環境マニュアル」を作るのでなく、「マネジメントマニュアル」として、品質・環境を一体化したマニュアルを作ればいいのです。
その時は、ただひとつにまとめるというのでなく、これまで何年か運用してきて、使い勝手の悪い点も見えてきているでしょうから、当然改善する必要があります。
ただ、ドッキングの際に注意する点がいくつかありますが、それはおいおいご紹介していくことにしましょう。
☆お知らせ☆
まぐまぐから
メルマガを発行しています。
『プロセスマネジメント』で生産性を上げるノウハウを、実例を交えて順次ご紹介していきます。
ぜひご購読ください。
購読申込みはこちらから
2010年05月16日
【プロセスのパラメーターをつかむ】
「プロセスのパラメーター」とは、
プロセスごとの処理能力のことです。
たとえば「加工プロセス」では、何種類もの品番を加工
しているでしょうが、
品番A:12個/Hr
品番B: 7個/Hr
・・・・・
といった具合です。
どの品番をどういう順序で作ったら、次工程との
能力バランスで、工程内仕掛品が時間当たりいくつ
増えるか、減るかということも見えてきます。
段取替えはできるだけ少なくしたいが、何時間作り
続けたら、仕掛品がどれだけ増えるか。
最適の連続生産時間は何時間か。
そういったことが全部シミュレーションできます。
時間当たり製造量の数値は、どこでも把握しておられる
でしょうが、
簡単な数式に当てはめることで、生産管理の精度が上がって
きます。
それができたら、必要に応じてIT化していけばよい。
最初から何百万円もする生産管理ソフトを導入すると、
絶対に失敗します。
まずはパソコンでスタートすることが賢明なやり方と
いえましょう。
プロセスごとの処理能力のことです。
たとえば「加工プロセス」では、何種類もの品番を加工
しているでしょうが、
品番A:12個/Hr
品番B: 7個/Hr
・・・・・
といった具合です。
どの品番をどういう順序で作ったら、次工程との
能力バランスで、工程内仕掛品が時間当たりいくつ
増えるか、減るかということも見えてきます。
段取替えはできるだけ少なくしたいが、何時間作り
続けたら、仕掛品がどれだけ増えるか。
最適の連続生産時間は何時間か。
そういったことが全部シミュレーションできます。
時間当たり製造量の数値は、どこでも把握しておられる
でしょうが、
簡単な数式に当てはめることで、生産管理の精度が上がって
きます。
それができたら、必要に応じてIT化していけばよい。
最初から何百万円もする生産管理ソフトを導入すると、
絶対に失敗します。
まずはパソコンでスタートすることが賢明なやり方と
いえましょう。