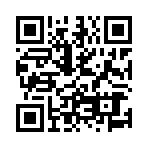2010年12月29日
【「標準」なくして「改善」なし】
「標準」とは「(現状で)そうあって当り前の状態」のことをいいます。
「先週は1日当り90個だったのに、昨日は120個上がった」
標準出来高が90個だったのなら昨日の努力を評価すればよい。
しかし、標準出来高が100個だったのなら、先週の上がりが低
かった原因を調べて手を打たなければならない。
1日100個が標準出来高の場合、120個にレベルアップするこ
とを「改善」と言います。
それに対して、90個の出来高を元の100個に戻すことは、「維
持管理」です。
「改善」と「維持」とでは、アプローチの方法が違ってきます。
標準より下がった(イレギュラー発生)の場合は、
(1)いくら(何%)下がったか [実態を掴む]
(2)原因分析 [原因はひとつではない。複数の原因を掴む]
(3)対策立案 [対策を急がない。複数の案を出して、評価する]
(4)対策実行
(5)効果確認
いわゆる「QCストーリー」二沿って行なえばいいのです。
標準をレベルアップする(改善)場合は
(1)理想状態を設計する
(2)現状と理想状態とのギャップを明らかにする
(3)ギャップを埋める
これは「デザインアプローチ」になります。
標準値(この場合は1日当り出来高100個)がはっきりしていなけ
れば、改善をするのか維持をするのか、とるべき行動が不明確に
なってくるのです。
☆「お問合せ」「ご質問」はこちらから ⇒ お問合せ
☆講演・研修のご依頼はこちらから ⇒ 講演・研修のご依頼
☆『工場カイゼンのヒント』バックナンバーはこちらで公開しています。
⇒ ここをクリック
「先週は1日当り90個だったのに、昨日は120個上がった」
標準出来高が90個だったのなら昨日の努力を評価すればよい。
しかし、標準出来高が100個だったのなら、先週の上がりが低
かった原因を調べて手を打たなければならない。
1日100個が標準出来高の場合、120個にレベルアップするこ
とを「改善」と言います。
それに対して、90個の出来高を元の100個に戻すことは、「維
持管理」です。
「改善」と「維持」とでは、アプローチの方法が違ってきます。
標準より下がった(イレギュラー発生)の場合は、
(1)いくら(何%)下がったか [実態を掴む]
(2)原因分析 [原因はひとつではない。複数の原因を掴む]
(3)対策立案 [対策を急がない。複数の案を出して、評価する]
(4)対策実行
(5)効果確認
いわゆる「QCストーリー」二沿って行なえばいいのです。
標準をレベルアップする(改善)場合は
(1)理想状態を設計する
(2)現状と理想状態とのギャップを明らかにする
(3)ギャップを埋める
これは「デザインアプローチ」になります。
標準値(この場合は1日当り出来高100個)がはっきりしていなけ
れば、改善をするのか維持をするのか、とるべき行動が不明確に
なってくるのです。
☆「お問合せ」「ご質問」はこちらから ⇒ お問合せ
☆講演・研修のご依頼はこちらから ⇒ 講演・研修のご依頼
☆『工場カイゼンのヒント』バックナンバーはこちらで公開しています。
⇒ ここをクリック
2010年12月13日
【工場カイゼンのカギは現場リーダーにあり】
工場でITが活かされているのは、「材料発注」と「入出庫管理」が精精。
「生産計画」は形としてIT化されていても、ほとんど全く使われていないのが実際のところです。
「生産指示」は、すべて現場リーダーのKKD(経験・勘・度胸)でなされているのです。
実際の生産指示がコンピュータでできない理由は、
生産現場ではイレギュラー(外乱)が常に発生しています。
・材料が入荷していない
・作業者の急な欠勤
・機械の突然の故障
・割込み注文
その都度データをインプットしていては、とても間に合わない。
現場リーダーの頭のコンピュータの方が早いのです。
しかし、現場リーダーも人間。能力に限りがあります。
KKDで処理できない部分については、「仕掛品」でリスク回避する。
イレギュラーが起こっても、納期遅れを発生させないためには、
仕掛品を持っておくしかないのです。
まさに仕掛品は「隠し預金」「埋蔵金」。
こういった事情を知らずに、
「整理整頓が悪い。通路がふさがっている。5Sを取り入れよう」
と叫んでも、何の効果を出すこともできないのです。
☆「お問合せ」「ご質問」はこちらから ⇒ お問合せ
☆講演・研修のご依頼はこちらから ⇒ 講演・研修のご依頼
☆『工場カイゼンのヒント』バックナンバーはこちらで公開しています。
⇒ ここをクリック
「生産計画」は形としてIT化されていても、ほとんど全く使われていないのが実際のところです。
「生産指示」は、すべて現場リーダーのKKD(経験・勘・度胸)でなされているのです。
実際の生産指示がコンピュータでできない理由は、
生産現場ではイレギュラー(外乱)が常に発生しています。
・材料が入荷していない
・作業者の急な欠勤
・機械の突然の故障
・割込み注文
その都度データをインプットしていては、とても間に合わない。
現場リーダーの頭のコンピュータの方が早いのです。
しかし、現場リーダーも人間。能力に限りがあります。
KKDで処理できない部分については、「仕掛品」でリスク回避する。
イレギュラーが起こっても、納期遅れを発生させないためには、
仕掛品を持っておくしかないのです。
まさに仕掛品は「隠し預金」「埋蔵金」。
こういった事情を知らずに、
「整理整頓が悪い。通路がふさがっている。5Sを取り入れよう」
と叫んでも、何の効果を出すこともできないのです。
☆「お問合せ」「ご質問」はこちらから ⇒ お問合せ
☆講演・研修のご依頼はこちらから ⇒ 講演・研修のご依頼
☆『工場カイゼンのヒント』バックナンバーはこちらで公開しています。
⇒ ここをクリック
2010年12月10日
【仕掛りを減らせば工場が儲かる】
「風が吹いたら桶屋が儲かる」ではありませんが、
[仕掛りが減る]→[作りすぎがなくなる]→[滞留時間が短縮]
→[リードタイム短縮]→[コストが下がる]→[工場が儲かる]
だからといって、「仕掛品がたまったから機械を止めよう」では、
納期遅れが発生するのは当り前。
・機械の突然の故障
・作業者の急な欠勤
・材料の発注忘れ
こういったイレギュラーの回避策として仕掛品を持つわけです。
「工程内不良を減らす」
「機械の停止ロスを減らす」
「人の動きのムダをなくす」
こういった地道な改善を進めることをしないと、仕掛品をなくす
ことはできません。
ただ、「作りすぎをヤメロ」というだけでは、納期遅ればかり発生さ
せてしまいます。
仕掛りを減らし、納期は勿論守る方法。
まずは仕掛品の上下限値を決めるところから始めてみましょう。
☆「お問合せ」「ご質問」はこちらから ⇒ お問合せ
☆講演・研修のご依頼はこちらから ⇒ 講演・研修のご依頼
☆『工場カイゼンのヒント』バックナンバーはこちらで公開しています。
⇒ ここをクリック
[仕掛りが減る]→[作りすぎがなくなる]→[滞留時間が短縮]
→[リードタイム短縮]→[コストが下がる]→[工場が儲かる]
だからといって、「仕掛品がたまったから機械を止めよう」では、
納期遅れが発生するのは当り前。
・機械の突然の故障
・作業者の急な欠勤
・材料の発注忘れ
こういったイレギュラーの回避策として仕掛品を持つわけです。
「工程内不良を減らす」
「機械の停止ロスを減らす」
「人の動きのムダをなくす」
こういった地道な改善を進めることをしないと、仕掛品をなくす
ことはできません。
ただ、「作りすぎをヤメロ」というだけでは、納期遅ればかり発生さ
せてしまいます。
仕掛りを減らし、納期は勿論守る方法。
まずは仕掛品の上下限値を決めるところから始めてみましょう。
☆「お問合せ」「ご質問」はこちらから ⇒ お問合せ
☆講演・研修のご依頼はこちらから ⇒ 講演・研修のご依頼
☆『工場カイゼンのヒント』バックナンバーはこちらで公開しています。
⇒ ここをクリック
2010年12月06日
【ISOは組織改革のチャンス】
【ISOは組織改革のチャンス】
社長の思い通りに動かない社員。
先代からのしがらみで、こちらの要求に応じてくれない取引先。
そういった相手には、
「うちはISO9001を取得することにした。このようにしてく
れないと、ISOを取得できない。」
こう言えば先ず間違いなく、
「ISOなら従うしかないな」
ということになります。
先代社長が会長になってもいまだ院政を敷いている。
社長の頭を通り越して社員に指示を与えるので、社長としては非常
にやりにくい。
そういった場合は、「責任・権限」の項で、会社の仕事を明確にし
て、文書化しておけばいいのです。
皆さん、結構真面目なので、文書化されたルールには従おうとする
傾向があります。
会長の口出しがなくなって、社長がのびのびと仕事を進められるよ
うになった例があります。
社長の思い通りに動かない社員。
先代からのしがらみで、こちらの要求に応じてくれない取引先。
そういった相手には、
「うちはISO9001を取得することにした。このようにしてく
れないと、ISOを取得できない。」
こう言えば先ず間違いなく、
「ISOなら従うしかないな」
ということになります。
先代社長が会長になってもいまだ院政を敷いている。
社長の頭を通り越して社員に指示を与えるので、社長としては非常
にやりにくい。
そういった場合は、「責任・権限」の項で、会社の仕事を明確にし
て、文書化しておけばいいのです。
皆さん、結構真面目なので、文書化されたルールには従おうとする
傾向があります。
会長の口出しがなくなって、社長がのびのびと仕事を進められるよ
うになった例があります。